ASD(自閉スペクトラム症)傾向のある子どもへの教え方は、ちょっとした工夫で大きく変わります。
私の息子(小3、ASD傾向あり)も、以前は「わかんない!」「もうやらない!」と投げ出すことが多く、家庭学習はいつもバトルのようでした。
でも、声かけのタイミングや言葉を変えるだけで、びっくりするほど反応が変わったんです。
この記事では、家庭で試行錯誤してわかった「ASD児への教え方のコツ」と「NGだった関わり」を、具体的に紹介します。
効果的な学習サポート法を知りたい方はこちら⬇️
「できない!やりたくない!」を乗り越える家庭学習習慣のつくり方
1. まず理解したいASD児の特性
子どもによって異なりますが、うちの息子には以下のような傾向がありました:
- 言葉の裏を読むのが苦手(比喩や曖昧な表現が通じない)
- 見通しがないと不安になりやすい
- 音や感覚に敏感で集中が途切れやすい
- 自分のペースを乱されると混乱しやすい
この特性を前提にした関わりが「教え方の第一歩」でした。
2. 教え方の「コツ」と「NG」早見表
| 場面 | NGな関わり | うまくいった工夫 |
|---|---|---|
| わからない時 | 「なんでこんなのも分からないの?」 | 「どこまでわかったか一緒に確認しよう」 |
| ミスを指摘するとき | 「また間違えたの?」 | 「このやり方、ちょっと変えてみようか」 |
| 取りかかる前 | 「早く始めて」 | 「あと○分で始めようか」と予告 |
| 言葉で指示 | 抽象的:「ちゃんとして」 | 具体的:「ノートを開いて1ページ目から書いてみよう」 |
| やる気がないとき | 「やる気ないならもうやめなさい!」 | 「1問だけ一緒にやってみる?」 |
3. 実際の声かけ例
NG例
- 「早くしてよ!」
- 「何回言ったらわかるの?」
- 「ちゃんと読んで!」
効果があった例
- 「次は何をやる予定だったっけ?」
- 「この問題、どこまでできた?」
- 「読んでて難しかったところ、一緒にチェックしようか」
4. 教材や環境の工夫
視覚で理解しやすくする
- ホワイトボードで「やることリスト」作成
- ポストイットで順番を視覚化
使った教材
- ▶ 教科書ワーク 小学3年
- ▶ Z会 小学生コース
- ▶ スケジュールカード・視覚支援ツール
実践で役立つ声かけや工夫について解説⬇️
5. 成功の鍵は「否定しない関わり」
ASD児には、ミスや失敗に敏感な子も多く、注意の仕方ひとつで心を閉ざしてしまうことがあります。
「間違っても大丈夫」「やり方を変えればできる」と安心感を持たせる声かけが、子ども自身のやる気や集中につながると実感しました。
うまくいかないときほど、「できているところ」や「努力している姿勢」に目を向けることが大切です。

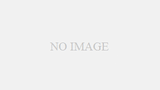
コメント