「勉強しよう」と言っても、机に向かえない。やっと始めたと思えば、すぐに立ち歩く。集中できない。読み飛ばす。ケンカになる。
発達グレー、ASD傾向のある息子と向き合う中で、私が何度もぶつかってきた壁です。
この記事では、そんな「家庭学習がうまくいかない」状況を、どんなふうに乗り越えてきたのか、我が家のリアルな工夫と変化をお伝えします。
「同じように悩んでいる親御さん」のヒントになれば幸いです。
特性に合わせた支援例はこちら👇
→ 感覚統合エクササイズで学習が変わった話
家庭学習がうまくいかない理由は「特性とのズレ」だった
最初に大切なことをお伝えしたいのは、家庭学習がうまくいかないのは「やる気がない」わけでも「甘えている」わけでもないということ。
うまくいかなかった我が家の最初の頃を振り返ると、息子には以下のような特性がありました:
- 集中が続かない(DCD・ASD傾向)
- 読み飛ばし・指示が通らない
- 感覚過敏で姿勢が崩れやすい
- 自信がなく「できない」とすぐに言う
これらの特徴は、一見「やる気がないように見える」ものです。でも実際には、学習スタイルや環境が子どもの特性に合っていなかったのです。
我が家のリアルな家庭学習の工夫5選
① 短時間×回数に区切る「集中の切れ目」を意識したスケジュール
学習の合間に短時間の感覚統合エクササイズを取り入れることで、集中力が持続しやすくなります。具体的なやり方は感覚統合エクササイズで学習が変わった話をご覧ください。
「30分がんばろうね」と言っても、無理でした。でも「5分だけやって、終わったらタイマー鳴らすよ」なら動けた。
今は以下のようにしています:
- 漢字5分
- 感覚統合エクササイズ3分
- 算数の計算5分
- 休憩(お茶・深呼吸)
② スケジュール・目標を視覚化して見える化
「何をすればいいか」が見える化されると子どもの不安が減ります。
「次なにやるの?」「もう終わった?」が多かったため、ホワイトボードで1日の流れと終わったらシールを使うようにしました。
本人が「見て分かる」ことで、安心して行動できるように。
③ 学習前に“体の感覚”を整える(感覚統合エクササイズ)
学習前に体をほぐし、落ち着きを促す感覚統合エクササイズは、我が家の重要なルーティンです。
息子はじっと座るのが苦手でした。そこで、学習前にスターフィッシュエクササイズやクロスクロールを取り入れるようにしました。
たった3分程度の運動でも、「落ち着いてから勉強する」感覚が少しずつ身についてきました。
④ 読解・文章題は「音読+対話式」で取り組む
読み飛ばしが多い子どもには、声かけや対話の工夫が効果的です。
文章問題は苦手中の苦手でした。読むのがしんどく、何が問われているかも理解できず、パニックになる。
「一緒に音読して、わかる言葉で話し合う」ことで理解が進みました。
⑤ 「できた!」を見える形に。ホワイトボードとごほうび表
成功体験の見える化は、子どものモチベーション維持に欠かせません。
終わった学習をホワイトボードに「花マル」で書くようにしました。シールを集めて、一定数たまったらごほうびへ。
結果的に、「がんばったら嬉しい」が実感できるように。
教材の導入ステップ👇
→ 家庭学習の導入に失敗しない!教材導入ステップ完全ガイド
教材も子どもの特性に合わせて選ぶ
スマイルゼミを使っていた時期もありましたが、「画面に集中できない」「適当に進める」ことが増えてやめました。
その後、以下のように使い分けるようになりました:
| 教材 | 合った理由 | 合わなかった理由 |
|---|---|---|
| スマイルゼミ | 音声・映像で刺激がある | 集中できず形骸化 |
| 公文(ぐーんとシリーズ) | 繰り返しで安心感 | 単調で飽きやすい |
| 教科書ワーク | 学校と連動しやすい | 量が多いとしんどい |
| Z会思考力ワーク | 親子で考えるスタイル | 難易度が高い |
スマイルゼミ公式はこちら→
実際に感じた変化と、まだ残る課題
- 集中できる時間が5分→15分に
- 自分から「やろう」と言う日が増えた
- 「わからない」から逃げず、言葉で説明できるように
一方で、気分の波で何もできない日や、定着しない日もあります。
でも確実に、少しずつ変化しています。
同じように悩むあなたへ伝えたいこと
家庭学習は、「子どもを伸ばす」前に「親の心が折れそうになる」こともあります。
でも、変わるのは子どもだけじゃない。親の視点と関わり方が変われば、子どもの反応も確実に変わっていきます。
がんばらせない、がんばり方を変える。その一歩が、未来を変えます。
関連記事
| \ 我が家のリアルな家庭学習工夫 / ・教材の選び方と導入法 ・やる気が出ない時の対処法 ・子どもの特性に合わせたアプローチ |

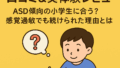

コメント