先取り学習が苦手な子の家庭学習の工夫10選|ASD傾向・感覚過敏の小学生の実例付き
「先取り学習が苦手でうまく進まない…」と悩む保護者の方は多いのではないでしょうか。特にASD傾向や感覚過敏がある子どもは、新しいことに対する抵抗感や集中力の波が大きく、先取り学習がうまくいかないことが珍しくありません。 しかし、工夫次第で「できた!」という成功体験を積み重ね、学習に前向きになることは十分可能です。この記事では、わが家の小学3年生(ASD傾向・感覚過敏あり)の実例を交えながら、先取り学習が苦手な子どもに効果的だった家庭学習の工夫10選をご紹介します。
家庭学習の工夫については以下の記事も参考に👇
わが家の子ども紹介
- 小学3年生(9歳)
- ASD傾向・DCD(発達性協調運動障害)・感覚過敏あり
- 姿勢が崩れやすく、読み飛ばしがちな傾向
- 集中力が続かず、先取り学習を強く嫌がる
先取り学習が苦手になる理由
先取り学習を嫌がる背景には、いくつかの理由があります。まず、内容が難しすぎて「できない」という不安や焦りが生まれます。 また、ASD傾向の子どもは変化に敏感で、新しい課題に対して強い抵抗感を持つことも多いです。さらに感覚過敏や注意力の波によって、集中が途切れやすくなり、途中で嫌になってしまうこともあります。
これらを無理に進めようとすると、親子ともにストレスが溜まり、ますます学習が嫌になってしまいます。そこで「その子のペースに合わせる」「成功体験を積み重ねる」ことを意識した工夫が重要です。
うまくいかなかった学習法の例
- スマイルゼミなどの通信教材を任せっきりにした → 適当に進めてしまい理解不足
- 先取り学習を強制した → 強く拒否されてやめざるを得なかった
- 一度で理解させようと急いだ → 焦りが伝わり逆効果に
これらの経験から、無理なく段階的に進めることと、子どもの「できた!」を積み重ねることが大切だと学びました。
やりたくない!を乗り越えた体験はこちら👇
→ 「できない!」を乗り越える家庭学習習慣のつくり方
→ 感覚統合エクササイズで学習が変わった話
家庭学習の工夫10選
① 繰り返し学習
同じ問題集や教材を2〜3回繰り返すことで理解度を深め、焦らず自信をつける。子どもが「わかった!」と思えるまで何度も取り組む。
② 見える化
チェック表や進捗ノートを用意し、達成した項目にマークやシールを貼って「できた!」を視覚的に実感させる。
学習習慣が激変した自作スケジュール表の話も役立ちます。
③ 付箋読み取り
文章題や長文はマーカーや付箋を使ってキーワードを視覚化。読むべき部分を明確にし、読み飛ばしを減らす工夫。読解力を伸ばす具体的な教え方のコツはこちらでまとめました。
④ 時間を短く区切る
1回の学習時間は15~20分程度に設定し、集中力が続く範囲で複数回に分けて取り組む。
⑤ 予習レベルの導入
授業の直前に軽く内容に触れる程度の予習を行い、新しい内容への抵抗感を和らげる。
⑥ ○で「できた!」
問題を解いたらすぐに「○」やシールをつけて、褒めることで成功体験を強化。
⑦ 学習ノート
親子で学習内容や気づきを記録し合い、振り返りの時間を設けて理解を深める。
⑧ 保留OK
難しい問題や苦手な単元は一旦保留にし、後から再挑戦するスタンスで無理をしない。
⑨ 生活と結びつける
学習内容を実生活の場面に結びつけて教え、理解の定着と興味関心を高める。
⑩ 感覚統合とセット
学習前にスターフィッシュなどの感覚統合エクササイズを取り入れ、体の準備を整えて集中力アップを図る。感覚統合エクササイズの効果的な方法についてはこちらをご覧ください。
タブレットをやめて改善した実例👇
→ スマイルゼミをやめた理由と、やめてから変わったこと
生活リズムと姿勢も大切
学習の効果を高めるには、生活リズムを整えることも欠かせません。わが家では6時起床・20時就寝の習慣を基本にし、毎朝の感覚統合エクササイズで姿勢と集中力が安定してきました。 姿勢が良くなると集中力が続きやすくなり、結果的に学習の質も向上します。疲れやすい場合は無理せず休憩を挟み、メリハリのある生活を心がけましょう。
実例紹介:わが家の変化
以前は先取り学習を無理に進めようとしたため、子どもは「できない!」と強く拒否していました。しかし上記の工夫を取り入れてからは、1日15分を目安に繰り返し学習し、マーカーで文章を追うなど視覚的な工夫もプラス。 結果として、少しずつ自信がつき、テストの点数も10点以上アップ。親子のコミュニケーションも増え、学習が楽しい時間に変わりました。
あわせて使える!おすすめ教材まとめ
今回ご紹介した工夫は、教材選びとも深く関係しています。
ここでは、ASD傾向・感覚過敏がある子でも取り組みやすかった教材を厳選して紹介します👇
- 📱 スマイルゼミ:視覚優位の子にも使いやすいタブレット学習
→ 【スマイルゼミ】公式ページはこちら - 📘 くもん『ぐーんと強くなる』シリーズ:短い問題文で安心。読解力UPにも◎
- 📗 Z会 小学生コース:シンプルな出題で、無理なく先取りできる
→ Z会公式サイトはこちら
→ Z会思考力ワークの口コミ&実体験レビュー|ASD傾向の小学生に合う?感覚過敏でも続けられた理由とは
まとめ:その子に合わせて工夫し続けることが大切
子どもによって合う学習法は異なります。うまくいかない時は「合っていなかっただけ」と捉え、焦らず様子を見ながら工夫を続けましょう。 今回紹介した10の工夫はどれも取り入れやすく、継続することで効果が期待できます。まずは一つから試し、子どもの様子を見て調整していくのがおすすめです。
また、生活リズムや姿勢の安定も学習の土台となるため、感覚統合エクササイズなども積極的に取り入れてみてください。 より詳しい方法や関連テーマは、他の記事もぜひ参考にしてください。
| 関連記事 \ 先取りが苦手な子に効いた工夫 / ・「やりたくない!」への対応法 ・Z会の活用事例 ・感覚過敏な子の学習サポート法 |
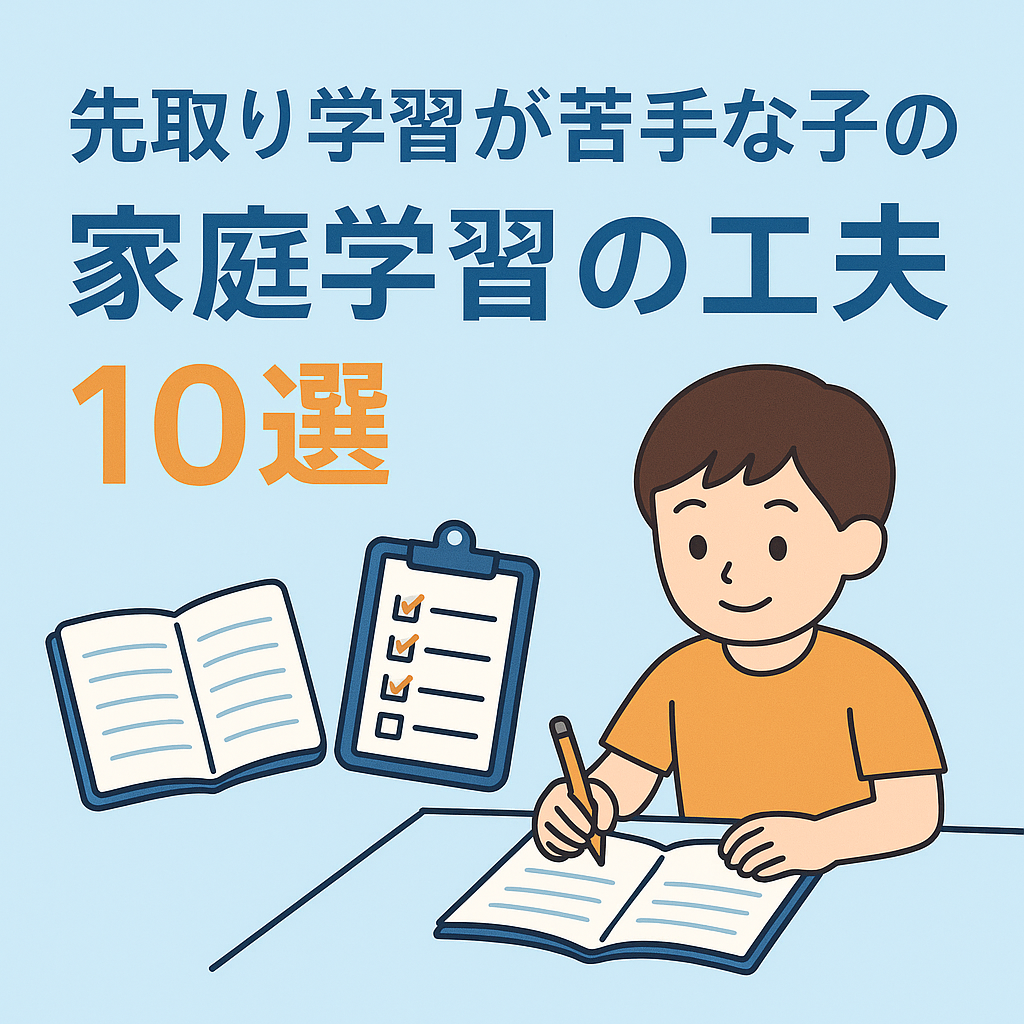
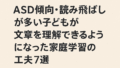
コメント